猫とは縁である。
以前飼っていた猫は私の勉強部屋の押し入れの上で生まれた。
母猫の名はサンボ。純粋なシャム猫でうちに貰われてきたときにすでに孕んでいて、数ヶ月後に勉強机に向かっている私のすぐ隣で1匹だけ子猫を生んだ。
母がその子猫の名前を付けた。名前はダイアナ。もちろんシャム猫だった。
たしかダイアナ妃の挙式があった頃だったと思うが、母は赤毛のアンの親友のダイアナから取ったという。
私はあまり気に入らない名前だったが、仕方がなくディアナとやや発音を変えて呼んでみたりしていた。
ディアナを生んだ母猫は間もなく手術をすることになり、しばらく入院していた。
私は生まれたばかりで手間のかかる子猫を相手に暖めたミルクを綿棒で湿らせて食事を与えたり、寒くないよう保温に気を付けたり細々とした世話を焼いていた。
母猫も無事退院してきて普通の生活に戻るが、その後はその子猫とは別段、親しい間柄になったわけではなく、相手の気分次第ですり寄って来たり、こちらもそれに応えて撫でていた程度だった。
むしろ私の方は部屋に置いてある油絵の道具(中には毒物になる樹脂などもあった)やら、大事にしているオーディオ装置を荒らされたくないので、どちらかというと邪険にしていた。
ディアナは生まれつきのやや寄り目で、近眼の人がそうするように鼻を押しつけんばかりに近づいて確認するところがあった。時折、眠っているときに上に乗ってきて、私の鼻に自分の鼻をすり寄せて臭いを嗅ぐ仕草をしたり、じぃーと私の顔を眺めていることもしばしばあった。ウトウトしながら私はその様子を薄目で観察し「何を考えているんだろうな?」と思いながらも構うこともなかった。
母猫のサンボは外出好きで、玄関先でいつも常に外へ出ようと機会を伺っていた。 誰かが出入りするたびに隙をうかがってパッと外へ飛び出すことが多かった。それでも最初はマンションの廊下あたりで済んでいたが、だんだん範囲を広げるようになり、やがて帰ってこなくなった。
ある日のこと、家族が全員が出かけて私とディアナだけの時があった。ソファーに座って頭や背中を撫でながら、ふと私は猫に言葉を教えてみようと思い付いて、ディアナを顔が向き合うように抱えて簡単な単語「おはよー」と何度か言い聞かせるように声をかけてみた。15度目くらいだろうか、ディアナはふと意志(あるいは意味合い)を持った目の色になり、舌で口の周りの舐めながらまるでのどの調子を確認するかのように「お、おはよー」とハッキリした口調で発音した。
今から考えれば滑稽だが、その時の私は「おぉ!やればできるんじゃないか!世間で猫がしゃべれないのは努力が足りないのかもしれないな」と、妙に納得してさらに言葉をしゃべらせようと再度「おはよー」と呼びかけた。しかし、言葉を発したのは後にも先にもこれ1回きりだった。帰宅した家族にそのことを話したが、まるっきり信じてもらえなかった。そりゃそうだろう、私だって他人から聞いただけではまずは信じられない。
しかし、後年に読んだ本の中で村上春樹氏が同じような経験をしたことが書かれていた。ある日、村上氏とシャム猫のみゅーずが昼寝をしていると、誰もいないはずの家で、すぐ隣から「だってそんなこと言ったって…ムニャムニャ」と言う声を聞いたのだという。驚いて、周りを確認したが誰もおらず、どう考えても隣に寝ている猫の寝言としか考えられなかった。確認しようと猫を起こして「今言ったのはお前か?」と問い質したが、猫の方は「何を言っているんだろう?」という目つきでその場からそそくさと逃げていったという。村上氏はその様子から何かを隠している印象を受けたと書かれていた。
私は経験があるのでこの話を信じることができる。
さらにそのみゅーずは村上氏に手を握ってもらいながらお産をしたと書かれていた。
みゅーずは陣痛が始まるとすぐに村上氏の膝にとんできて「よっこらしょ」という感じで座椅子にもたれるような格好で座り込み、両手をしっかりと握ってやると、やがて一匹また一匹と子猫を生み出したという。
お産ではないが、ディアナは私の手を握ったまま逝った。
その日は、すでに実家を出ていた私は久しぶりに実家へ戻っていた。その頃は実家に帰ること自体が滅多になかったが、不思議な事にたまたま帰ったその日にディアナは亡くなった。
その時、リビングでくつろいでいると、突然隣の部屋から妹が「ダイアナがが死んじゃう」とベソをかきなながら飛び込んできた。急いで向かうと敷かれた布団の上で息絶え絶え絶えに苦しそうなディアナがいた。その姿に何をしたらよいか判らない私は手を差し出した。その差し出した手の人差し指に肉球を重ね、ディアナは大きく目を見開き、必死に私の手(指)に爪を立ててしがみつき、最後の一息を吐くとあの世に旅立っていった。
結局、この猫は揺りかごから棺桶まで私が見届けたことになる。 よほど縁のあった猫だったのだろう。村上氏は話せるはずの猫が普段は話せない振りをしていると考えているようであるが、私の考えは少し違う。深い縁の者と一緒にいる時に、折に触れて瞬間瞬間に前世の記憶が蘇るのだろうと思う。それもよほどの縁のある者と一緒の時のある瞬間にだけだろう。
前世が存在はまだ証明されていないが、仮に存在するとした方が色々な物事の筋が通りやすく、また存在した方が楽しいのでそう思うことにしている。
結局のところ猫とは縁だと思う。
今、妹のところで飼われているサラという猫は私が家を出た後に飼われた猫で。全く縁がないらしく私が近づいても懐かず、むしろ怯えさえする。別段いじめた記憶もないのにこうも嫌われると「縁のない猫なんだな」と一人納得している。
猫を飼いたいとは思いつつできない私は、ひょっとしたら現世では縁のある猫がもう居ないのではないかと危惧しているのである。



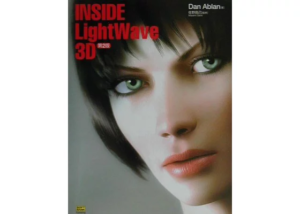



コメント